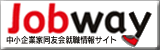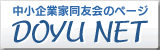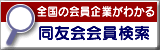同友会ニュース−活動報告
人を生かす経営全国交流会に参加して
人が育つ企業と地域をつくる
 平成20年11月20日~21日 /滋賀県大津市
平成20年11月20日~21日 /滋賀県大津市
メインテーマ 『人が育つ企業と地域をつくる 』
~「労使見解」の精神を柱にした企業の総合的実践をすすめよう~
基調講演:東大名誉教授 大田 尭 (おおた たかし)氏
テーマ 「共に生き、共に育つ」 ~生命(いのち)のきずなを~
*人間は「自己中心、自己本位」(あらゆる生物の特徴である自己防衛のため)の一面と「孤 独を嫌う」(人にあてにされ、共に関わり合わないと生きれない)一面の両面をもっている。
生命はみな違う。『自己中心同士が共に生きる』のが持続出来る人間社会。
*「人々が競争の中でバラバラになっている」今の時代や、「恐慌や自然災害に耐える」ため には、「人間関係を濃くする」施策が必要。
自然災害や経済危機の時に「人間関係が疎遠」で人が孤独であると危険(殺人、テロ、自殺)。
*従来共同体とは違う「新しい質、新しい内容の人間関係の修復」が処方箋。
*「新しい地域づくり、人間関係づくり」多様なパターンが考えられる。
*不特定多数でなく、お得意様を大切にする手堅い「密度深い信頼」で深い味のあるものへ。
*「違いを認識」した付き合いに活力が生まれる。
なかなかうまく行かないが、「ワンクッション置く」とうまくいく。
いくら言っても思うようにならないのが、「人間・生物の特徴」であると認識する。
*新しい時代をつくるための『三つのヒント』
ヒント①『違い』。いっぺんに死ぬことはない。必ず誰かが生き残ることにより、支えあう。
違いの受入れは大変難しいが、克服的出来たら生きのびれる。
ヒント②『関わる』。「心の響き合いのある関わり」で人類の文化・社会情報の同一性が貫かれ、大脳に伝わり、生きのびる知恵が生まれる。
ヒント③『自ら変わる』力を一人一人の生命個体は持っている。それを尊重しあい、わきまえて付き合う中で、新しい地域像、会社像を発見する。
『違い』=「自主」、『関わる』=「民主」、『自ら変わる』=「連帯」…同友会の精神。
【感想】90歳とは思えない活力と大局観、新しい時代のヒントに出会えた。
Ⅱ.第1分科会に参加して
テーマ「一人ひとりの学びと自覚が企業を、地域を変える」
~歴史と社会を学び、考える力をつける社員「共育」実践~
報告者 滋賀同友会 やわらぎ住宅㈱ 山崎 裕基氏
*本物の社員共育。自ら気づき、「考える社員」。おしつけはいけない。人間としての土台を築けば、自分で考え、行動出来る。そして、地域に広めて行く。
【感想】宗教的なものを感じたが、翌日には、共育の徹底、社長の本気に共感できた。
Ⅲ.グループ長を体験して
【感想】問題提議のレベルが高く、自分でも見失いかけた時、他のメンバーに進行支援してもらえた。全国行事ともなるとレベルが高いと思った。誘導することもなく、皆に発言して頂き、リラックスした雰囲気の中で、問題点を深め、実践につながる討論にチャレンジ出来たと思う。
美保テクノス㈱ 清水 勉
鳥取同友会から2名参加しました!
 ■特に心に残ったこと
■特に心に残ったこと
・「今回の不況(恐慌)は、自己中心(競争社会)から、共生社会への転換期ではないか。
よって、人間関係の密度を濃くするような政策・対策をすべき。
ただし、昔の長屋意識のような関係でなくても良い。(それで戦争に向かい一丸となってしまったのだから)
また、その政策・対策の中には、エコへの配慮が必須。特に、医療・福祉・教育…そういう人の絆を強めるラインの強化が大切。
そして、新しい地域づくりの創造をしていかなくてはならないのだ。(そのヒントは、命の特徴に求めるべし。心の響き合いのある関わり合いを創造していかなくてはならない)
・社員に対して、「教育してやろう」「同化させよう」という姿勢は、命に対してとても失礼な考え方。
・「共に生きるどころじゃないよ!お金だ!」となりがちな中で、共生を重んじる同友会活動は、とても大切。
・信頼できないのは、相手の可能性を信じていないから。
社員の可能性を信じて、社員が輝くステージづくりをしなければならない。
・人は、言われたことはしない。すべきだ、大切だと思ったことをする。
私は何をしてもらいたいのか、そのためには何を気付いてもらいたいのか。
それを明確に心に描き、伝わるように伝えていかなければならない。
■明日から実践しようと思ったこと
目標1:社員の顔を見たら、その日の体調が分かるくらいになる!
→ 目的:社員と了解・合意できる関係作づくりのため。
→ 実践:現場に入り、社員と顔を合わす、目を合わす。名前を呼ぶ。会話する。
目標2: 経営理念実現のためにできること、すべきことは何かを、社員と共有する
→ 目的:「人と知と印刷技術が織りなす喜び世界の実現」(経営理念【仮】 の実現)
→ 実践:・経営計画を、社員と共に作り、共に実行し、共に評価し、共に見直す(PDCA)。
その枠組みを用意する。
・社員の特性を積極的に知るようにし、各社員が喜んで出社できるよ
うにするに はどうしたら良いのか、常に留意するようにする。
・忙殺されないようにし、いつも周囲への配慮を心がける。
・苦手な社員に対しても、避けず、可能性を信じ、共に輝けるステー
ジづくりをする。
綜合印刷出版㈱ 植木 仁美